#131 第6回 Webサイト発注の教科書 :Webサイトが「いつまで経っても公開できない」構造的な理由

「プロジェクト停滞」
【3つのフォーカス】
1.停滞の原因: Webサイト制作が「分業化」された結果、多様な専門家間の「翻訳」と「バケツリレー」で情報がこぼれ、プロジェクトが停止するメカニズム。
2.最大の敵: プロジェクトを停滞させる最大の原因は、外部の制作会社ではなく、発注者側の「社内協力体制の欠如」と「意思決定の遅れ」にある。
3.担当者の使命: Web担当者が、社内外の専門家をつなぎ、意思決定を促す「橋渡し役(トランスレータ)」としてリーダーシップを発揮する重要性。
=====================================================【キーワード】#Webプロジェクト停滞 #Web制作分業化 #橋渡し役 #社内調整ミス #意思決定の遅れ #トランスレータの役割
=====================================================
~なぜ、あなたのWebサイトは「完成しない」のか?~
「Webサイト、いつになったら完成するんだろう?」
「担当者が変わるたびに、話が振り出しに戻ってしまう…」
あなたの会社で、そんな声が上がっていませんか? あるいは、Webサイト制作を依頼したものの、最初の勢いだけですぐにプロジェクトが停滞し、公開の目処が立たなくなってしまった、という経験はないでしょうか。
第3回から第5回にかけて、Webサイトが期待外れに終わる原因として「丸投げ」や「準備不足」を指摘しました。しかし、どれだけ綿密な準備をしても、なぜかプロジェクトがスムーズに進まないことがあります。
その原因は、Webサイト制作の根底にある「複雑な分業化」という構造的な問題に隠されています。そして、その問題の多くは、実は発注者側の社内にあるのです。
Webサイト制作は「ひとりの職人技」から「多様な専門家の協業」へ
かつてWebサイト制作は、ひとりの「Webデザイナー」がデザインからコーディングまでを担う、ある種の「職人技」でした。しかし、Webサイトの機能が高度化し、スマートフォン対応や、裏側で複雑なシステムが動く現代においては、ひとりで全てを完結させることは不可能になりました。
今のWebサイト制作は、まるで家を建てるのと同じです。
建築家、大工、電気工、配管工、左官工…それぞれが専門家として連携しなければ、家は完成しません。
Webサイトも同様です。ちょっと家建てるときのイメージで制作会社にどのようなスタッフがいるか、カンタンに書いてみると…。
●Webディレクター: 建築家のように全体の設計図を描き、プロジェクトを統括します。多くの制作会社が担当窓口としています。
●UI/UXデザイナー: 家族の暮らしやすさ(ユーザー体験)を考え、間取りや内装のデザイン(見た目と使い勝手)を設計します。
●フロントエンドエンジニア: 窓やドア、壁といった、目に見える部分を正確に組み立てていきます。
●バックエンドエンジニア: 水道やガス、電気といった、目に見えないインフラ(システムの裏側)を構築します。
●コンテンツストラテジスト: 家族の歴史や未来の暮らしをヒアリングし、住む人が何を語る家にするか(Webサイトに何を載せるか)を考えます。
このように、現代のWeb制作は、多様な専門家による「分業化」で成り立っています。
もっとも制作会社によって様々な「肩書き」の専門家(なかにはカタカナのよくわからないのもありますけど…)がいますし、小さな会社だと兼務していることもあるわけですし、部分的にアウトソースしている場合もあるでしょう。
このようにそれぞれがそれなりに専門化、高度化しているので、かつてのように、ひとりですべて…というのはもはや無理なのです。ま、そもそも普段のビジネス自体がもはや一社のみで成立しなくなっているのと同じと言えば同じようなものです。
プロジェクトを停滞させる最大の原因は「発注側社内の遅れ」
この分業化は、 Webサイトの高度化には不可欠な一方で、さまざまなワナをはらんでいます。
ワナと書きましたけど、複数の人間が関わるプロジェクトになったということなので、当然そこにはいくつかのトラブルになりそうなことが潜んでいるという意味です。
特に、中小企業がWebサイト制作を依頼する際に直面する「あるある」です。
■翻訳者としての「Webディレクター」の役割を軽視するワナ:
制作会社のWebディレクターは、発注者であるあなたの意図を正確に理解し、それをクリエイターたちが理解できる「技術的な言葉」に翻訳する、いわば「トランスレータ(翻訳者)」の役割を担います。
優秀なWebディレクターは優秀な翻訳家なのです。逆もしかりです。技術的なまたはクリエイティブな要素を会社のweb担当者にわかりやすく、ビジネスの用語?や一般的に通用している用語に変換して伝えてくれるはずです。
しかし、Web担当者が「直接、デザイナーやクリエイターと話したい」と要望してくるケースが時々あります。
気持ちは分かります。デザインについて直接指示を出して、その場で確認したい。
しかし、これをやるとクリエイターたちは確実にいわゆるオペレーター化します。「言われた通りにやっておけば文句は出ないだろう」と考えるようになり、結果としてできあがったサイトは、デザインセンスのないもの、よく見かけるモノになってしまうというオチもつきます
(残念ながら…。デザインの話はここでいづれすることになりますが、なぜかデザインに関しては誰でも口出しできることになってしまっているようです。「口出し障壁」が低い。ちゃんとプロフェッショナルな領域があるとこれを読んでいる賢明なweb担当者はおわかりでしょうが…)
Webディレクターという窓口をきちんと通すこと。これが、あなたの思いを正確に伝え、クリエイターにクリエイティビティを発揮させるための、最初のルールです。
■「情報のバケツリレー」による伝達ミス:
担当者であるあなたからWebディレクターへ、そしてWebディレクターから各専門家へ…と情報は伝わります。この過程で、伝達ミスや、微妙なニュアンスのズレが生じることは避けられません。Webサイトの方向性や、デザインの意図といった重要な情報が、バケツの穴から少しずつこぼれ落ちていくようなものです。
これはプロジェクトの進行においては自明のことというか、織り込み済みのことなのです。残念ですがゼロにはできません。
いかにしてこのズレを少なくするか?を考えるべきです。(様々なプロジェクトマネジメントの理論もあることはご存じかと思います。ここではそんな話ではないのですが…)
しかし、Web担当者が、制作会社のWebディレクターとの連携を疎かにし、Webサイトの目的やコンテンツの意図を曖昧に伝えてしまうと、この「情報のバケツリレー」は、より大きな伝達ミスと認識のズレを生んでしまいます。
「言った↔言わない」のモヤモヤ感もよく生じる場面です。先にも書きましたがWebデイレクターは翻訳家ですから、こちらが伝えたことがどのような形でアウトプットされるのかも翻訳してもらうことにしましょう。厳密にはこの翻訳におけるズレがあるわけなので、逆にそのズレを踏まえておくことができるというメリットもあります。
ただ、Webのデザインに関する限り、ある種の「よい裏切り」があるだろうと私は思っています。
会社のWeb担当者が思い描いたデザイン通りにできなかったということは必ずしも悪いことではなく、これぞクリエイティブというある種の違った視点を提示してくれることもあるのです。
これはズレとかミスとかではなく、「解釈」「翻訳」と考えるべきことなのかもしれませんが…。
■「社内協力体制の欠如」という最大の停滞要因:
プロジェクトが遅れる最大の理由は、やはり発注者側の社内に大きな要因があります。Web業界では「総務部が窓口になるとサイトはちゃんとできない」と、半ばジョークのように言われることがあります。これは、総務部の人たちが無能だからではありません。彼らは、Webサイトというプロジェクトの「決定権」を持っておらず、社内のあちこちの部署にお伺いを立てる「御用聞き」になってしまうことが多いからです。(総務部の人スミマセン。必ずしもすべてがそうだというわけではないことは重々承知しています)
会議のセッティングですら、関係者全員の都合を待つ。全員が都合つかなければ開かれない。しかし、内容によっては全員が出席する必要なんてないはずです。
このような状況では、Webサイトの仕様やサイト構成図の確認一つにしても、時間がかかります。制作期間を仮に3ヶ月と想定してプロジェクトが始まっても、発注者側の確認や意思決定が滞ることで、半年、一年と伸びてしまうことも珍しくありません。制作会社は、3ヶ月の工数を想定して見積もりを出しているのに、発注者側の遅延で大きな負担を強いられます。納品完了となってからの請求・支払いが多いWeb制作の世界では、これはもう真っ赤かの赤字です。
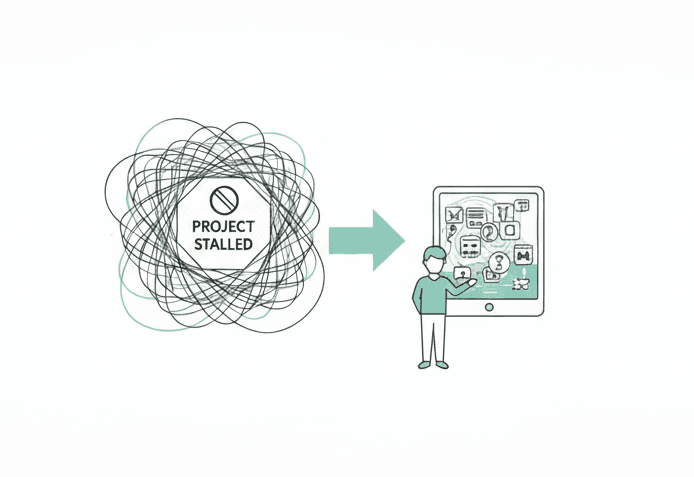
プロジェクトを停滞させない!Web担当者が果たすべき「橋渡し役」の使命
では、どうすればこの「分業化のワナ」を避け、プロジェクトを円滑に進められるのでしょうか?
Web担当者であるあなたが、この複雑な分業化の「橋渡し役」になること、これしかありません。ただし、その役割は、制作会社のWebディレクターを助けることだけではありません。あなたがまず、自社のWebサイトプロジェクトの「リーダー」として、社内の協力体制を築き、迅速な意思決定を促すことが最も重要なのです。
1. 指示系統を明確にする:
Webディレクターは、制作会社との窓口として不可欠です。一方で、サーバー会社、すでに利用しているSaaS会社、社内の他部署とのやりとりまで、すべてWebディレクターに丸投げすることは避けるべきです。どこまでが制作会社の管轄で、どこからがあなたの会社が責任を持つべきか、指示系統をはっきりさせましょう。
詳細なweb制作に関する知識は必要ないと何度も申し上げていますが、知識はあるに越したことはないですが、ここでも特別な知識は必要ありません。全体の流れがわからなければ、制作会社のディレクターに相談すればいいのです。どういう手順でなにをしていけばよいのか?そこで、社内の事情を鑑みて指揮系統を明確にしていけばいいのです。
2. 迅速な意思決定を促す:
Webサイト制作が進行していることを、社内の関係部署や上司に定期的に共有し、重要な決定事項については、迅速に回答が得られるような仕組みを整えましょう。
言うは易し。なかなか上席や忙しい人たちにwebサイトの情報共有は理解してもらえない。在宅ワークが多くなっているような場合、オンラインでの社内ミーティングでは、議題として一番最後だったりすると、時間切れで、次の週まで持ち越しなんてことも起こりえます。社内に皆がいる環境であれば、ミーティング終了後にちょっと相談って感じで話持ちかけられたりできるわけです。
なるだけ、事前にwebサイトの重要性を社内にアピールしておくことも必要です。
Webサイト制作は、関わるすべての人間が「チーム」として協業するプロセスです。担当者がこの「橋渡し役」としての使命を果たすことで、Webサイトは「なんとなく」で終わることなく、関わった全員が誇りを持てる「成果」へと繋がるのです。
次回は、Web制作の現場で最も多くのすれ違いを生む、デザインに関する問題について掘り下げます。
=====================================================
【Webサイト発注の教科書】
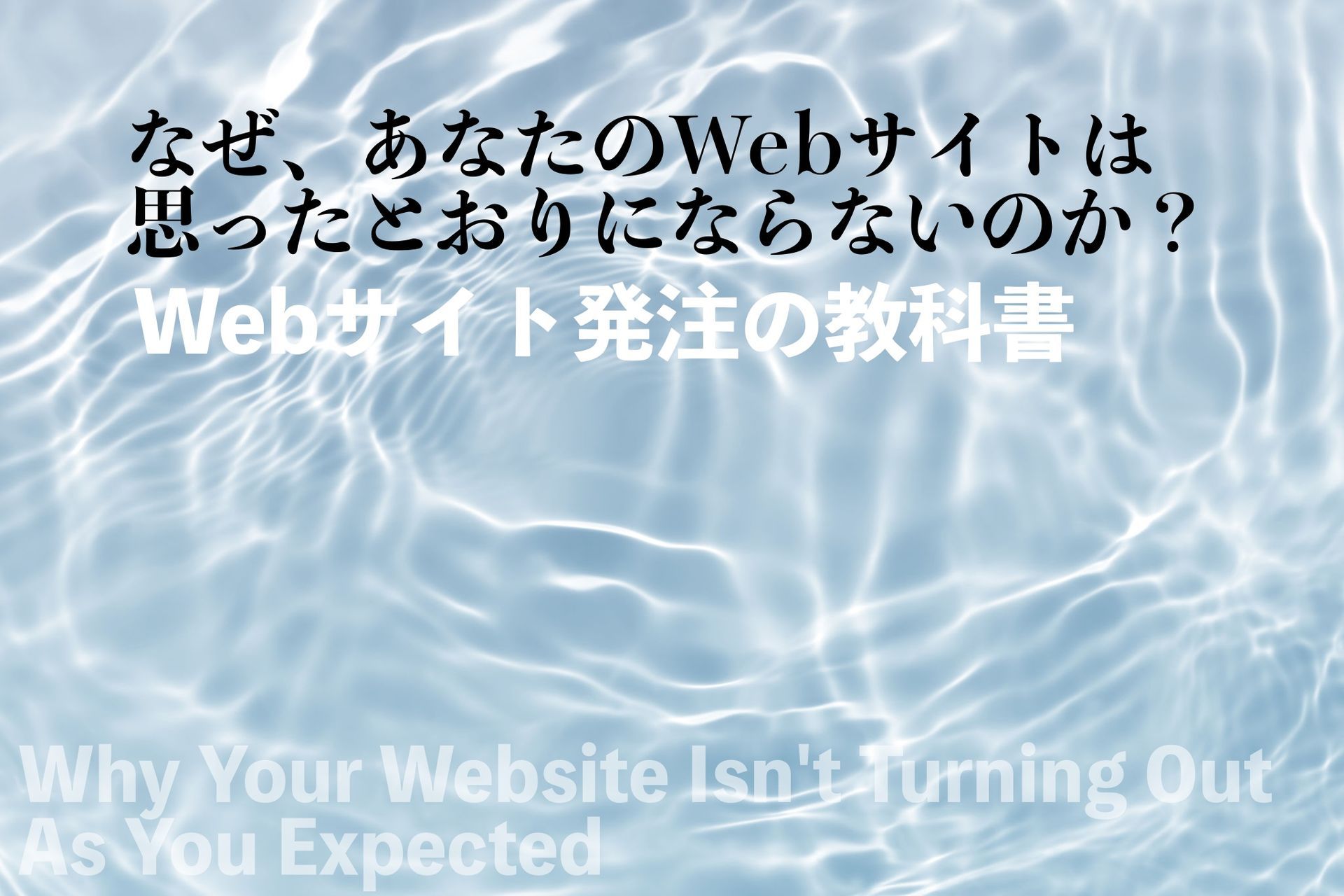
上手に発注し、良好な関係を築き、
愉しく仕事を進めるためのノウハウ満載!
発注の仕方ひとつで、あなたの会社の
Webサイトは劇的に変わる!
「制作会社に任せたのに、なぜか成果が出ない」「費用ばかりかかって、サイトが会社の『お荷物』になっている」—この問題の根源は、Webサイトの技術ではなく、発注者側の「無意識の誤解」と、制作現場の「構造的なすれ違い」にあります。ちょっと長めの文章ですが、10回プラスαで書いてみました。Webサイトを構築、運用していく際に、役立つ、愉しめる。そして、しくじらないためのノウハウです。
